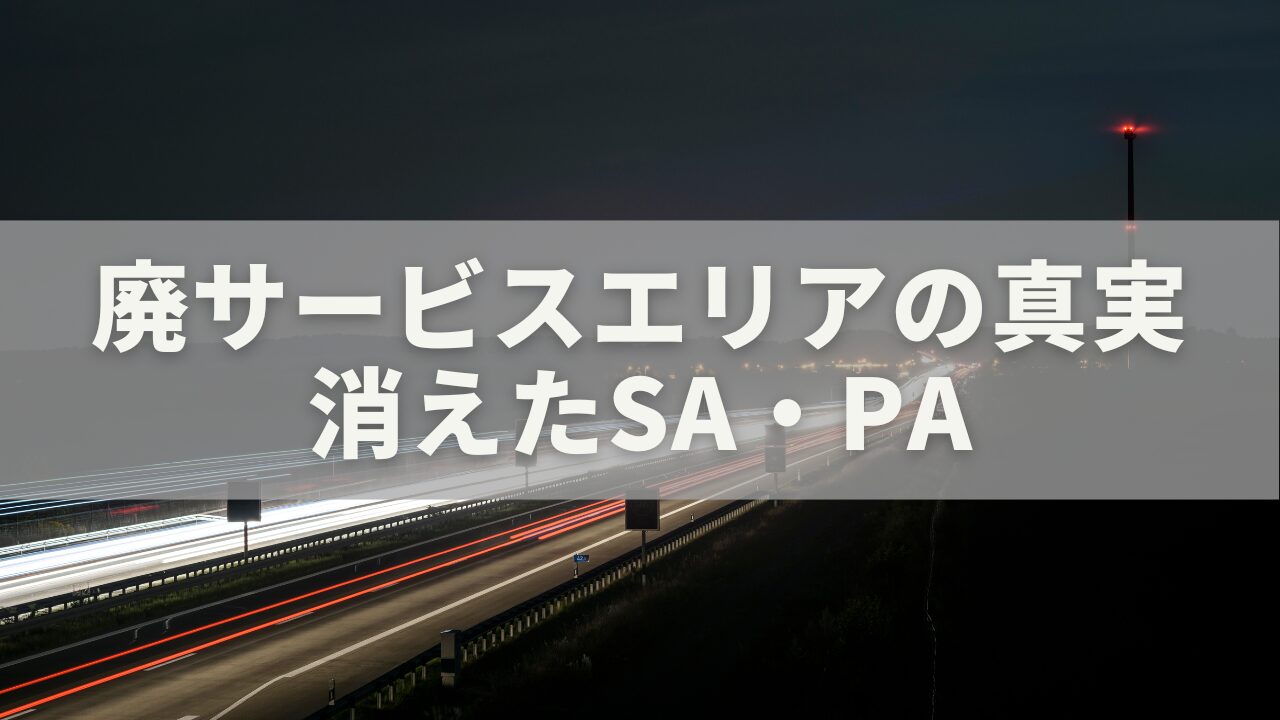かつて多くのドライバーに愛されたサービスエリアやパーキングエリアの中には、今はもう存在しない場所があります。
廃止されたサービスエリアの裏には、経営破綻、労働問題、人口減少、そして新型コロナウイルスなど、さまざまな社会的要因が潜んでいます。
この記事では、東北道の佐野SA、北陸道の徳光PA、小矢部川SA、そして名神高速の廃PA群といった実例を通して、「なぜ消えたのか」そして「今、私たちが学ぶべきことは何か」を丁寧に解き明かします。
単なるノスタルジーではなく、変化の時代を生き抜くための“未来へのヒント”を探る旅へ、あなたも出かけてみませんか。
廃サービスエリアとは?閉鎖の裏にある“時代の変化”
サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)は、高速道路を利用するドライバーにとって欠かせない休憩施設です。
しかし、時代の変化とともに一部の施設が役割を終え、「廃サービスエリア」となって姿を消していきました。
ここでは、その背景にある時代の変化や経済的な要因を、わかりやすく整理して解説します。
サービスエリアとパーキングエリアの違いを整理
まず最初に、サービスエリアとパーキングエリアの違いを簡単に整理しておきましょう。
サービスエリア(SA)は、約50km間隔で設置され、ガソリンスタンドやレストラン、売店などを備えた大型の休憩拠点です。
一方でパーキングエリア(PA)は、15km間隔程度で設けられ、基本的にはトイレと自動販売機が中心の小規模施設となっています。
とはいえ、近年はこの境界があいまいになりつつあります。
パーキングエリアにも大手カフェや地元食材のレストランが入るケースが増え、かつての“簡易休憩所”というイメージは過去のものになりつつあります。
| 分類 | 設置間隔 | 主な施設 |
|---|---|---|
| サービスエリア(SA) | 約50kmごと | トイレ・給油所・レストラン・おみやげ売店など |
| パーキングエリア(PA) | 約15kmごと | トイレ・自販機(+軽食店など) |
この違いの縮小こそ、現代のサービスエリアが抱える「変化の象徴」といえるのです。
なぜサービスエリアが廃止されるのか?
では、なぜこれまで多くの利用者に親しまれてきたサービスエリアが廃止されてしまうのでしょうか。
理由の一つは、社会構造そのものの変化です。
日本全体で人口が減少し、特に地方では車の利用者も減っています。
この結果、高速道路の交通量も低下し、売上が伸び悩むサービスエリアが増加しています。
さらに、近年では「道の駅」や「大型ショッピングモール」といった競合施設の台頭により、高速道路上の休憩所で買い物をする必然性が薄れてきているのも現実です。
交通量・経営・人材不足――3つの衰退要因
廃サービスエリアの背後には、主に3つの要因が複雑に絡み合っています。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 交通量の減少 | 人口減少や物流ルートの多様化により、利用者数が減少。 |
| 経営環境の悪化 | 維持費や人件費の高騰、コロナ禍による売上減少。 |
| 人材不足 | 24時間運営を支える人手が確保できず、営業時間短縮や撤退が相次ぐ。 |
とくに地方の施設ほどこの影響を強く受けています。
交通量が減れば売上が下がり、採算が取れなくなれば人員削減や閉鎖へとつながる。
この悪循環こそが、廃サービスエリアを生む最大の要因です。
つまり、廃止は“失敗”ではなく、“時代の必然的な結果”でもあるのです。
【事例1】東北道・佐野サービスエリア―ストライキが招いた崩壊劇
かつて人気を誇った「佐野サービスエリア上り線」。
2019年の夏、この場所で日本中を騒がせた“異例のストライキ騒動”が起きました。
お盆という一年で最も利用者が多い時期に営業が停止するという前代未聞の出来事は、全国の高速道路関係者に衝撃を与えました。
お盆に突如発生したストライキの真相
発端は2019年8月14日。
東北自動車道の佐野藤岡インター〜岩舟ジャンクション間にある佐野SAで、突如として売店やレストランが営業を停止しました。
原因は、運営会社「ケイセイ・フーズ」とその親会社との内部対立です。
親会社の資金繰り悪化により、商品の仕入れや給料支払いが滞るという異常事態が発生しました。
この状況を打開しようと、当時の総務部長・加藤正樹さんが取引先と交渉し、支払い前倒しなどをまとめた覚書を提出。
しかし、社長がその合意を覆し、加藤さんを一方的に解雇。
これに反発した従業員60名が一斉にストライキを敢行し、店舗は完全閉鎖に追い込まれました。
| 発生日 | 主な原因 | 影響 |
|---|---|---|
| 2019年8月14日 | 経営陣と従業員の対立、部長解雇 | 全店舗営業停止、メディアが連日報道 |
まさに“お盆休みのど真ん中”というタイミングも相まって、利用者からは戸惑いと不満の声が相次ぎました。
「名物の佐野ラーメンが食べられないなんて…」という声がSNSでも拡散され、問題は一気に全国ニュースへと発展しました。
内部対立と労働環境の歪み
このストライキは、単なる給与問題ではありませんでした。
背景には、現場を支える従業員と、数字だけを重視する経営陣との深い溝がありました。
従業員たちは「現場の声を無視する経営体制」に不信感を募らせており、加藤さんの解雇をきっかけに一気に噴出しました。
さらに、当時の社長が「ストライキするなら別の人を入れる」と発言したことで、対立は決定的に。
代わりに投入された臨時スタッフは現場運営に慣れておらず、売店や厨房は混乱状態に陥りました。
結果として、経営陣と従業員の信頼関係が完全に崩壊したのです。
ストライキ期間中、加藤さんは休業中の従業員に対して自腹で支援金を支給。
「会社のためではなく、人のために働く」という信念が、多くの従業員を再び奮い立たせました。
運営会社交代と復活までの道のり
39日間という長期戦の末、2019年9月23日にストライキは終結します。
経営陣が退陣し、加藤さんが復職することで、ようやく営業が再開されました。
しかし、信用を失った「ケイセイ・フーズ」は契約満了をもって撤退。
以後は、「日の丸サンズ株式会社」が新たに運営を引き継ぐことになります。
| 期間 | 出来事 |
|---|---|
| 約39日間 | 営業停止(ストライキ継続) |
| 2019年9月23日 | スト終結、営業再開 |
| 2020年3月 | ケイセイ・フーズ契約終了 |
現在の佐野SAは、「日の丸サンズ」が運営する新体制で通常営業を続けています。
店舗やサービスの刷新も行われ、再び多くのドライバーに親しまれる場所となりました。
この事件は、“労働環境の改善なくしてサービスの質は守れない”という教訓を残したのです。
【事例2】北陸道・徳光パーキングエリア―夢の“ハイウェイオアシス”の終焉
日本初の「ハイウェイオアシス」として誕生した北陸自動車道・徳光パーキングエリア。
開業当初は「高速道路の新時代を切り開いた」と称賛されましたが、時代の波に飲み込まれ、惜しまれつつもその幕を閉じました。
ここでは、その華やかな誕生から衰退、そして再生の道のりをたどります。
全国初のハイウェイオアシスとしての輝き
徳光PAは1990年、石川県白山市に開業しました。
松任海浜公園と直結する形で設けられ、日本初の「ハイウェイオアシス」として全国的な注目を集めた場所です。
当時としては珍しく、高速を降りずに温泉や海浜施設を利用できるという画期的な仕組みでした。
上り線側の「まっとう車遊館」には、海鮮市場・おみやげコーナー・劇場などが併設され、まるで観光地のような賑わいを見せていました。
| 開業年 | 特徴 | 主な施設 |
|---|---|---|
| 1990年 | 全国初のハイウェイオアシス | 海鮮市場・温泉・劇場・レストラン |
この頃は「高速道路の休憩所=観光地」とも言えるほど、家族連れや観光客でにぎわっていました。
徳光PAは、まさに“地域の顔”として輝いていたのです。
地元依存と価格競争がもたらした衰退
しかしその後、徳光PAを取り巻く環境は急速に変化します。
周辺地域に大型商業施設や観光拠点が次々と誕生し、かつての「珍しさ」は失われていきました。
さらに、施設の老朽化や運営コストの増加が経営を圧迫。
運営会社は2度の倒産を経験し、2019年には商業施設が閉鎖、建物は解体されてしまいました。
| 時期 | 出来事 | 影響 |
|---|---|---|
| 2000年代 | 近隣競合施設の増加 | 来客数減少 |
| 2010年代 | 運営会社の経営悪化 | 倒産・施設閉鎖 |
特に問題となったのは、地域観光客に過度に依存したビジネスモデルでした。
地元の物産や海産物は魅力的でしたが、観光シーズン以外は人が集まらず、年間を通じた収益が安定しませんでした。
また、地元の商店街との競合や、価格の高さに対する不満も相次ぎ、利用者離れが進んでいきました。
まさに、「地域密着」の理想が、経営リスクにもなってしまった例です。
跡地に見る観光モデルの限界
その後、徳光PAは「白山ゲートウェイとくみつTaaanto(タント)」として再出発しました。
ただし、かつてのような大型施設ではなく、コンビニエンスストアとファストフード店を中心とした小規模再開発にとどまりました。
2022年には再び営業が軌道に乗り始めたものの、往年の賑わいを取り戻すには至っていません。
この変化は、“観光地型サービスエリア”というモデルが時代とともに限界を迎えたことを象徴しています。
| 再開業年 | 新名称 | 主な施設 |
|---|---|---|
| 2020年 | 白山ゲートウェイとくみつTaaanto | セブンイレブン・すき家 |
今の徳光PAは、派手さを抑えた“現実的な運営”を選択しています。
これは、一見地味に見えても、地域と共存しながら持続可能性を高める賢い選択と言えるでしょう。
徳光の歴史は、「豪華な観光施設」から「身近な生活拠点」へと進化した、日本のサービスエリアの縮図なのです。
【事例3】北陸道・小矢部川サービスエリア―老舗企業を倒したコロナの現実
北陸自動車道の「小矢部川サービスエリア」は、1973年の開通当初から地域とともに歩んできた歴史ある施設でした。
しかし、新型コロナウイルスの影響により、47年の歴史を持つ運営会社が破産に追い込まれるという衝撃の結末を迎えました。
ここでは、老舗企業がなぜ破綻に至ったのか、その背景を紐解いていきます。
地域密着運営だった小矢部川SAの歴史
小矢部川サービスエリア(上り線)は、富山県小矢部市に位置し、北陸道でも特に利用者の多い区間にあります。
運営を担っていたのは「小矢部サービスステーション株式会社」。
創業以来、地元特産品を使ったおみやげや飲食事業を展開し、地元経済に深く根ざしてきました。
例えば、富山名物「ますのすし」や「いもまんじゅう」などを自社製造して販売するなど、地域文化の発信拠点としての役割も果たしていました。
| 運営会社 | 設立 | 特徴 |
|---|---|---|
| 小矢部サービスステーション | 1973年 | 地元密着・自社製造の特産品販売 |
しかし、近隣に大型の新しいサービスエリアが次々と開業し、徐々に利用者が減少。
さらに時代の変化に合わせたリニューアルも進まず、施設の老朽化も深刻化していきました。
経営悪化とパンデミックによる破産
小矢部川SAを直撃したのは、2020年の新型コロナウイルス感染拡大でした。
外出自粛と観光需要の消失により、利用者数が激減。
もともと薄利で運営していたサービスエリアにとって、この売上減少は致命的でした。
2020年5月8日、小矢部サービスステーションは事業を停止し、破産申請の準備に入ると発表。
負債総額は約2億5千万円に上り、富山県内で初のコロナ関連倒産として報じられました。
| 発生年月 | 出来事 | 影響 |
|---|---|---|
| 2020年5月 | 運営会社が破産申請 | SA上り線が営業停止 |
| 2020年12月 | 新運営会社による再開 | コンビニ中心の新体制へ |
当時、下り線は別会社の運営で通常営業を続けており、対照的な運命をたどりました。
上り線の休業はドライバーからも惜しまれ、「もうあの味が食べられないのか」とSNSで話題になりました。
残された施設の今と再生への課題
破産から半年後の2020年12月、新たな運営会社「ジェック経営コンサルタント株式会社」により営業が再開しました。
新体制では、運営コストを抑えつつも、利便性を重視した再構築が行われています。
1階にはコンビニとおみやげ販売スペース、2階には地元グルメを提供する軽食エリアを配置。
シンプルながらも快適な設計で、かつての賑わいを少しずつ取り戻しつつあります。
この事例は、“コロナ時代における持続可能なサービスエリア運営”のひとつの答えを示しています。
つまり、大規模施設よりも、経済的に無理のないスモールモデルへと転換することが、これからの時代に必要な発想なのです。
小矢部川SAの再生は、「地域愛」×「現実的な経営」が両立した成功例といえるでしょう。
【特集】名神高速に眠る4つの廃パーキングエリア
名神高速道路は、日本で最初に開通した高速道路として知られています。
1965年の全線開通以来、交通の大動脈として多くのドライバーに利用されてきました。
しかしその裏には、役割を終えて静かに消えていった「廃パーキングエリア(廃PA)」の存在があります。
ここでは、名神高速に実在した4つの廃PAを紹介し、なぜこの道路だけに廃止が集中しているのかを探ります。
上石津・番場・甲良・桜井――消えたPAたち
名神高速道路には、かつて4つの小規模パーキングエリアが存在していました。
それが「上石津PA」「番場PA」「甲良PA」「桜井PA」です。
いずれも昭和期に設置された非常に簡素な設備で、現在の感覚からすれば信じられないほど質素な施設でした。
| 名称 | 所在地 | 設備 | 廃止理由 |
|---|---|---|---|
| 上石津PA | 岐阜県大垣市 | ゴミ箱のみ、トイレなし | 融雪装置整備により不要に |
| 番場PA | 滋賀県米原市 | 小型車5台分の駐車場 | 米原JCT建設で撤去 |
| 甲良PA | 滋賀県犬上郡 | トイレのみ | 利用率低下 |
| 桜井PA | 滋賀県東近江市 | 不明(資料不足) | 老朽化・交通量変化 |
特に上石津PAは、自販機もトイレもない“幻のPA”として語り継がれています。
当時の目的は、ドライバーの休憩よりも「緊急時の待避スペース」としての機能が中心でした。
名神に集中する「廃止の構造的理由」
なぜ名神高速だけに、これほど多くの廃PAが存在するのでしょうか。
その理由は、この道路が「日本初の高速道路」だったことにあります。
当時の設計基準は現在よりもはるかに緩く、道路幅も狭く、設備も最小限でした。
そのため、開通当初に設けられたPAは、現代の交通需要に対応できなくなったのです。
| 時代 | 主な特徴 | 影響 |
|---|---|---|
| 1960年代 | 簡易PAが多数設置 | 最低限の設備で運用 |
| 1980年代 | 交通量の増加 | 小規模PAが機能不全に |
| 2000年代以降 | 改良・再編成 | 老朽PAが順次廃止 |
また、名神沿線は交通網の改良が進み、ジャンクションやスマートICの整備に伴い、物理的にPAのスペースが確保できなくなった場所もあります。
つまり、「歴史的構造の限界」と「現代化の波」が重なった結果が、この廃PA群なのです。
現地を訪れる際の注意点と見学マナー
現在も一部の廃PA跡地には、舗装跡や出入口の痕跡が残されています。
しかし、これらの場所はすべて高速道路の管理区域に含まれており、一般人の立ち入りは禁止されています。
特に上石津PA跡地はNEXCO中日本の管理施設となっており、許可なしでの立入は法令違反となるおそれがあります。
見学を行う場合は、安全な公道や展望所から観察するのが鉄則です。
また、写真撮影をする際は、地元住民や交通の妨げにならないよう配慮する必要があります。
- 管理区域には立ち入らない
- 地域住民に配慮して静かに見学する
- ゴミの持ち帰りを徹底する
廃PAは単なる遺構ではなく、“日本の高速道路文化の生きた記録”なのです。
廃サービスエリアが映す“日本の交通と経済”の現在地
これまで紹介した事例から見えてくるのは、サービスエリアの衰退が単なる一企業の問題ではないということです。
その背景には、日本全体の人口構造、経済活動、そして地域の在り方の変化が深く関わっています。
「廃サービスエリア」は、いわば日本社会の縮図ともいえる存在なのです。
衰退の裏にある地域経済と人口減少
まず注目すべきは、地方の人口減少と高齢化です。
地方部では、若者の都市部流出により交通量が減少し、これがサービスエリアの採算性を直撃しています。
国土交通省のデータによると、2050年までに全国の約2割の市町村で人口が半減するとされています。
このことは、地域交通や生活インフラの維持が難しくなることを意味します。
| 課題 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 人口減少 | 地方の労働人口が流出 | 交通量・利用者数の減少 |
| 人材不足 | サービス業従事者の確保が困難 | 営業時間の短縮・サービス低下 |
| 経済縮小 | 地元消費の減退 | 収益減による撤退リスク |
特に地方サービスエリアでは人手不足が深刻で、運営を維持できず閉鎖されるケースが増えています。
この問題は、単に交通施設の問題ではなく、地域社会の縮図としての意味を持っています。
“人が減る”ことは、“道が減る”ことに直結しているのです。
次世代SAに必要な新しい価値とは
サービスエリアの未来には、「機能の再定義」が求められています。
かつては“休憩のための施設”でしたが、これからは“目的地としての施設”へと進化する必要があります。
実際に、NEXCO各社では「地域共創型サービスエリア」構想を進めており、地元住民が一般道からも利用できる「ウォークインゲート」を整備しています。
また、テクノロジーの導入も急速に進んでいます。
AIによる需要予測、無人店舗、キャッシュレス決済、そして自動運転車の休憩拠点としての設計など、“未来対応型インフラ”への進化が進んでいます。
| 分野 | 導入される新技術 |
|---|---|
| 運営管理 | AI・IoTによる在庫・人員最適化 |
| サービス | キャッシュレス・モバイルオーダー・無人販売 |
| 環境対応 | 太陽光発電・EV充電・再生エネルギー活用 |
一方で、こうした効率化が進むほど、人との関わりが薄れていく懸念もあります。
だからこそ、「地域らしさ」や「人の温かみ」をどう残すかが、次世代SAの大きなテーマといえるでしょう。
ドライバーが支える「利用する応援」という選択
サービスエリアを守る力は、実はドライバー自身にもあります。
地方の小さなSAを意識的に利用するだけでも、その地域の経済に貢献できます。
たとえば地元産の食品を購入したり、地域限定メニューを楽しむことが、運営を支える大きな支援となります。
- 地元グルメ・特産品を選んで買う
- SNSで魅力を発信する
- 無人店舗や新サービスを積極的に利用する
これらの小さな行動が、結果として地域経済を循環させ、施設の存続を後押しします。
“利用すること自体が支援になる”という新しい意識が、これからの高速道路文化を育てていくのです。
まとめ:廃サービスエリアは“終わり”ではなく“進化の通過点”
この記事で紹介した廃サービスエリアや廃パーキングエリアの歴史は、単なる「終わりの記録」ではありません。
それはむしろ、日本の高速道路文化が進化を続ける中で生まれた「過渡期の証拠」です。
かつての繁栄、そして衰退の裏には、社会の変化や経済の構造転換が確実に反映されています。
廃止の影にある学び
佐野SAのストライキは、労働環境と組織の在り方を問う出来事でした。
徳光PAの衰退は、観光依存型モデルの限界を示しました。
そして小矢部川SAの破産は、パンデミックという外的要因に対応する経営の柔軟性を考えさせられる事例でした。
| 事例 | 象徴する教訓 |
|---|---|
| 佐野SA | 現場の声を軽視する組織は崩壊する |
| 徳光PA | 観光偏重のリスクと地域共存の必要性 |
| 小矢部川SA | 環境変化への対応力が生死を分ける |
どの廃止も「失敗」ではなく、「次の世代への教科書」なのです。
名神の廃PA群もまた、日本の道路史における“試行錯誤の跡”として記録され続けています。
次に訪れるサービスエリアの未来
これからのサービスエリアは、単なる休憩施設を超えた「地域共創の場」として進化していくでしょう。
たとえば、一般道からもアクセスできる“地域交流型SA”、災害時には避難拠点として機能する“防災型SA”、そして再生可能エネルギーを活用する“エコSA”。
それらは、すでに全国各地で静かに動き始めています。
同時に、AI・IoT・ロボティクスといった技術革新が運営を支え、持続可能な社会インフラへと進化していくはずです。
しかし、どんなに便利になっても、人の温かさが欠けては意味がありません。
サービスエリアが「旅の思い出の一部」であり続けるためには、地域の個性と人の心を大切にする姿勢が欠かせません。
“変化を恐れず、進化を受け入れる”こと
廃サービスエリアは、過去の遺物ではなく未来への道標です。
それは、「何を残し、何を手放すのか」という社会全体への問いかけでもあります。
そして私たち一人ひとりのドライバーも、その進化の一部です。
次にSAやPAに立ち寄るとき、そこに込められた努力や歴史に少し思いを馳せてみてください。
あなたの一杯のコーヒーやおみやげ購入が、誰かの仕事を支え、地域を生かし、未来の高速道路文化を形作っていくのです。
それこそが、廃サービスエリアが私たちに残した“最大のメッセージ”なのかもしれません。